自社大工。
社員大工。
工務店について調べる中で、そんな言葉を目にしたことはありませんか?
今や、注文住宅において高性能は当たり前。デザイン性の高い住宅を設計できる工務店やハウスメーカーも増えている。それでは、突出したものがなく横並びになりつつ住宅業界において、何を判断材料に住宅会社を選べばよいのでしょうか?
ここでようやく、「いちばん大切なのは、品質ではないか?」と人々は考え始めます。実際に、仕様の上では高い性能も優れたデザインも、施工技術がともなわなければ意味がありません。
そこで、最近になって『大工』の存在にスポットが当たるようになりました。
Contents
“家を建てる人”大工

設計図どおりに柱や梁を組み、壁や床の下地となる部分を仕上げていく。建物の要である主要な構造部を手掛ける、家づくりの中心的な存在。構造強度や断熱・気密性能など、安全性や快適性を左右する住まいの性能は、この“躯体部分”に大きく関係しています。家の仕上がりの美しさも、大工の腕ひとつで変わります。
つまり、どんな大工が建てるかによって、家の品質は良くも悪くもなるのです。
ところが、今この大工という職人が、全国的にも減少傾向にあります。
その中でも、本当に腕のよい大工はひと握り。加えて、現代の高性能住宅に必要な知識とスキルを備えた大工というと、さらに希少な存在です。
大工工務店とは?
こうした中で、自社で大工を雇用している工務店の存在が、改めて注目されています。
大工工務店と営業工務店
『大工工務店』という正式な名称があるわけではないのですが、代表自身が大工、もしくは代表は大工でないものの大工を自社で雇用していて、プランニングから大工仕事、現場管理まで自社で行う工務店のことを、その他の工務店と区別して『大工工務店』ということがあります。
対して、プランニングや現場管理は自社で行うものの、大工仕事を外注に出している工務店のことを『営業工務店』などといったりします。
現代の工務店のほとんどは、この『営業工務店』というスタイルをとっており、『大工工務店』は大工と同様に希少な存在となっています。

大工工務店の強み
大工工務店には以下のような強みや、施主に対するメリットがあります。
意思疎通が図りやすい
プランニングから施工までの流れを社内で一貫してコントロールできるため、施主側の要望が伝わりやすく、要望に対しての可否もその場で判断できるため、1つひとつのやり取りがスムーズ。
一般的に、現場監督は複数の現場を同時進行で管理するため、いつでも同じ現場にいるとは限りませんが、大工工務店の場合は大工自身が現場管理を兼ねているので、「常に現場を見てくれている」「いつでも会って話ができる」という安心感があり、関係性を築きやすいというメリットも。
品質が安定する
大工仕事を外注している場合、すべての注文住宅を同じ大工が請け負っているとは限りません。いつもの大工の手が空いていなければ、どこかから空いている大工を引っ張ってきて、仕事をしてもらうことになります。当然ながら、大工1人ひとりの技術力にも差があります。
その点、大工工務店ならすべての注文住宅を同じ大工が施工する、あるいは社内できちんと育てた大工が施工することになるため、施工品質にバラつきが出にくいというメリットがあります。
会社の姿勢そのもの
なぜ、今は大工を雇用する工務店が少ないのか。これはとてもシンプルで、大工を雇用すれば、それだけ人件費の負担が大きくなるから。
それでも大工を自社で雇用するのは、工務店として何よりも品質を重視しているということ。ただ数をこなすのではなく、すべての現場で最高の仕事をするという矜持を感じます。常に仕事のある状態を維持しなければならないので、それだけの営業力=地域での信頼があるという証でもあります。
外注の大工は何が違う?

それでは、『外注大工』というのはどういう存在なのでしょうか。
特定の企業に属していない大工は、個人事業主。個人事業主として工務店などから業務を請け負い、一定の期間、現場に常駐する形で仕事をします。
職人の他にも、クリエイティブ系や営業系に多い働き方ですね。
報酬は“給与”ではなく“日当”や“手間(坪)請け”という形になりますが、この金額は大工によって違い、熟練の大工ほど単価は高くなります。今、腕のいい大工は引く手あまたなので、見積書の木工事の単価が極端に安い場合は、大工の質を疑ってもよいかもしれません。
専属大工という場合もある

『自社大工』と『専属大工』は、似ているようで少し違います。
自社大工はその名の通り、工務店が自社で直接雇用している大工です。社内スタッフとして常時在籍しており、教育や指導も一貫して行われています。
一方、専属大工は外部の個人事業主ではあるものの、特定の工務店の仕事を専属、あるいはメインで請け負います。実質的にはチームの一員として継続的に関わっており、施工方針などの共有もされているケースが多く、一定以上の規模の会社であれば、徒弟制度などの教育体制を設けて大工を育成している場合も。
大工といっても技量はさまざま

さらに、一口に大工といっても、普段している仕事の内容や技術力には大きな差があります。
寺社仏閣を手掛ける宮大工を始め、木の性質を知り尽くし、ノミやカンナ、ノコギリを使って手刻みで木材を加工し、伝統構法の家を建てることができる昔ながらの大工。
手刻みの技術はないものの、今の住まいに必要なスキルを持って、丁寧かつ正確な仕事ができる大工。
ハウスメーカーの専属として、規格の決まった家の骨組みを図面どおりに組み上げていく大工。
それぞれ活躍の場は違いますが、大切なのは、それぞれの場所において高い品質を提供できる大工に家を建ててもらうことです。
これからの家づくりに求められる視点

性能やデザインももちろん大切。だけど、それを「実際に形にしてくれるのは誰か」という視点は、決して無視できません。戦後から続いた、安価な住宅を大量生産する時代はとうに終わりました。素材の美しさを最大限に表現する“木の家”や、細かく丁寧な作業が必要とされる“高気密高断熱住宅”。これらの家には、人の手による緻密な仕事が宿っています。
「誰が建てても同じ」は、もはや通用しません。大工の棟梁が中心となり家を建てていた時代と同じように、これからは信頼のおける大工のいる住宅会社こそが、施主から求められる時代になっていくのかもしれません。
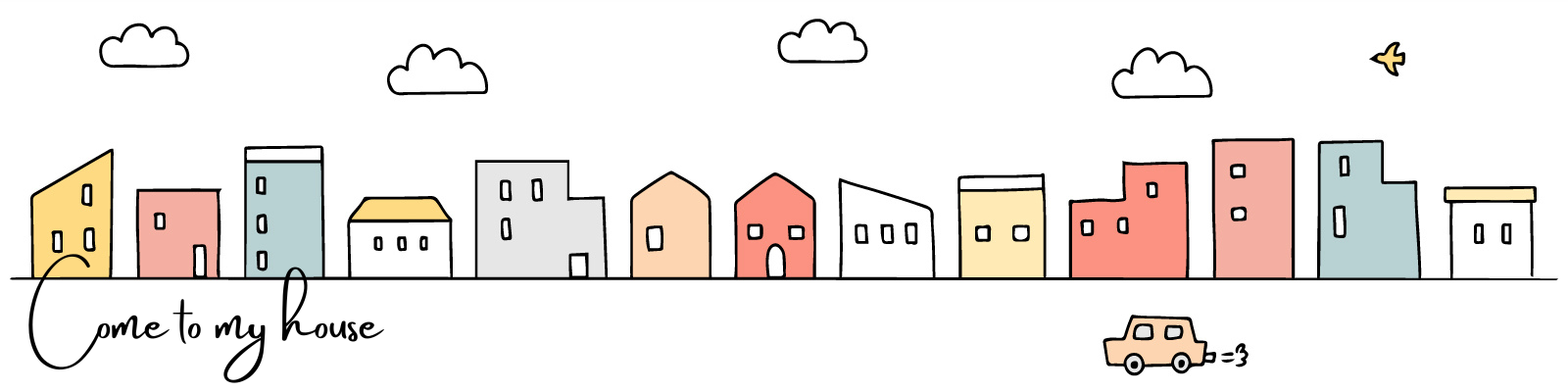
One thought on “今、自社大工が熱い!?希少だからこそ価値がある職人技術”
現在コメントは受け付けていません。