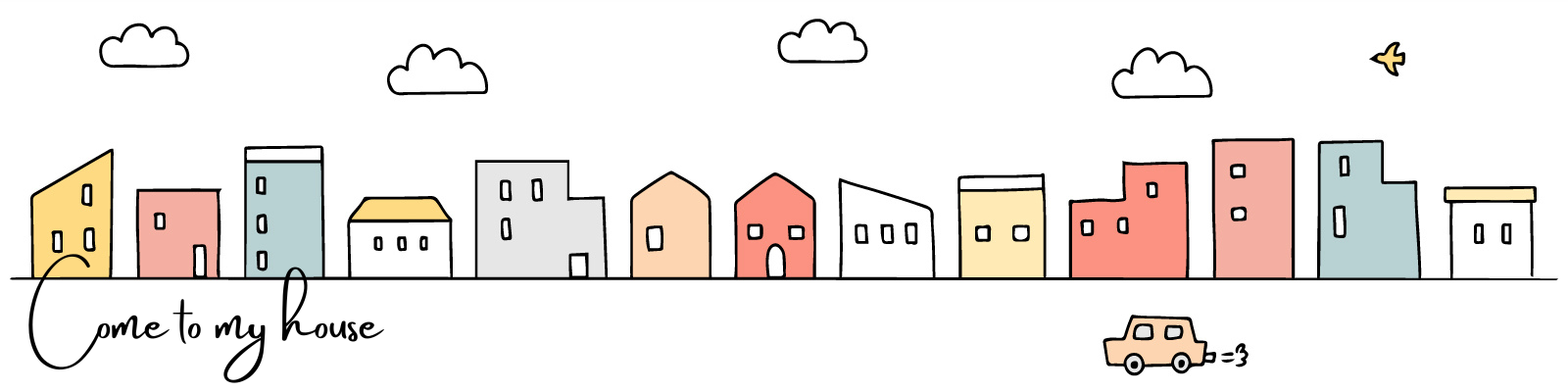暑すぎる夏。26℃でエアコンをつけていると、なんとなく体がだるく感じる。
「冷房病?」と思って1℃だけ上げてみると、もう暑くて我慢できない。
夜も寝苦しくて一晩中エアコンをつけているけれど、ふとした瞬間に電気代の不安が頭をよぎる――。
夏になると、そんなふうに家の中でさえ安心して過ごせない日があります。
そんなとき思い出すのは、あの日、仕事で訪ねた古民家のこと。蝉の声を聞きながら長い石畳を通り抜け、玄関のチャイムを押す。「はーい、どうぞ」という声が聞こえ、玄関戸を開けて一歩足を踏み入れる。
その瞬間、全身がひんやりとした空気に包まれる。
白川郷や五箇山を訪れたことのある方なら、わかるのではないでしょうか。エアコンがついているわけでもないのに、なぜか涼しい。あの不思議な感覚は、今でも強く心に残っています。
Contents
なぜ、古民家は夏涼しいのか
古民家は、高温多湿な日本の気候に合わせて生まれました。
『徒然草』で兼好法師が残した言葉に「家のつくりようは夏をもって旨とすべし」とあるように、日本の住まいは本来、夏をいかに涼しく過ごすかを出発点に考えられています。

では、実際どのような設計の工夫により、夏涼しい家が生まれたのか。具体的に見ていきましょう。
呼吸をする
古民家は、現代住宅に使われているようなビニールクロスや合板フローリングではなく、三和土の土間や土壁、無垢材、畳といった自然素材でつくられています。
これらの素材はすべて微細な穴をもつ『多孔質』で、湿度が高い時には湿気を吸い、湿度が下がると湿気を吐き出すという性質を持っています。まるで、家全体が呼吸しているかのよう――。
この天然の調湿機能が、じめじめとした夏でもサラリとした空気をつくってくれるため、新建材の家に比べて暑さを感じにくいのです。
熱を逃がす
古民家は、今の家に比べて天井がかなり高くつくられています。暑い空気は上昇する性質があるため、夏の熱気は天井高く立ちのぼり、小屋裏や腰屋根の窓から外へと抜けていきます。
この『煙突効果』が、生活空間に熱気がたまりにくく、過ごしやすい空間づくりに一役買っています。

風を通す
古民家には、『田の字』と呼ばれる間取りが多く見られます。襖で仕切って個室として使ったり、すべて開け放って広間として使ったりと、実用性を重視したつくりでもありますが、実は夏になると、これらの襖をすべて取り払ってしまう家も多いのです。
玄関を開けた瞬間、田の字の奥まで抜ける視界。そして、通り抜けていく風。
このように部屋全体をひと続きにできる間取りも、夏の風通しをよくするための工夫のひとつなのです。
日差しを遮る
日本家屋によく見られる、深い軒や庇。これは、夏の高い日差しを遮りつつ、冬の低い日差しは室内に取り込むことができるという、古くから受け継がれてきた知恵のひとつ。
太陽の動きを計算し尽くした設計により、「光は通すが、熱は入れない」という“ほどよい遮光”が実現されています。
現代の注文住宅に活かす“古民家の知恵”

家の中を風が抜けるように設計するには“余白”が必要です。一方で、日差しをやわらげる工夫には“陰影”が欠かせません。どちらも、ただ性能を追求するのではなく、心地よさを設計するための大切な要素です。
空間設計
現代の住宅では、間仕切りを極力なくしたオープンな間取りが主流となりつつあります。家全体の空調効率を上げることが目的ですが、これは夏になると襖を取り払う古民家の考え方と非常に近く、あとは窓の配置や形状に気を付けることで、風通しもぐっとよくなります。
風通しをよくするには、開口部を対角線上に設けるのが基本。吹き抜けや階段の上部に窓を設けることで、煙突効果を狙えます。
さらに、空気を滞留させない“回遊動線”や風が一直線に抜ける“ストレート動線”を組み合わせることで、家の中に自然な風の流れが生まれます。
外観・外構計画
いくら間取りを工夫しても、そもそも立地として風通しが悪ければ意味がありません。
密集した住宅地では、仮に敷地が狭くても、できるだけ中庭や通り庭を設けて風の通り道を確保してあげましょう。
» 外とつながる暮らし。庭のある家で心に潤いを。

また、直射日光は室内温度を上げる直接的な原因となるため、深い軒や庇で日射を遮るか、古くから日除けに使われてきた『すだれ』や『よしず』のように、“窓の外側”で日差しを遮る工夫を取り入れましょう。
たとえば、オーニングや窓シャッター。落葉樹や緑のカーテンなら、植物の蒸散能力によって周囲の温度を下げることもできます。
エアコン効率を高めるには、室外機もできるだけ軒下などの日陰になる位置に設置しましょう。
内装・インテリア
もちろん、内装に自然素材を用いるのも効果的。三和土や土壁は、今ではあまり使われることがありませんが、無垢フローリングや漆喰、珪藻土を壁や床に使用することで、じめじめとした空気を変えることができます。
» 無垢フローリングは大変?後悔しないために知っておこう
風通しには窓の形状も関係してきます。デザイン性が高い窓として人気の縦すべり出し窓なら風をキャッチしやすく、上げ下げ窓なら1つで風の入り口と出口をつくることができます。
また、観葉植物にも蒸散能力があるので、インテリアに合わせてリビングや寝室に大きめのグリーンを飾ってみては?
エアコン効率を高める住まいの性能

ここまで、古民家の知恵を応用した“夏涼しい家のつくり方”についてお話してきましたが、これらはすべて、基本的な住宅性能を高めておくことが前提です。
古民家は確かに夏涼しいのですが、その分、冬の寒さは段違い。だから、夏だけでなく冬も過ごしやすい住まいにするためには、住宅性能を高めることが必要不可欠。
高い断熱性で外気の影響を抑え、高い気密性で室内の空気が逃げるのを防ぐ。それによってエアコンの負荷を軽減し、快適かつ省エネルギーな暮らしを実現しましょう。
» これからの時代の選択肢、省エネ住宅はどう選べばいい?
“古さ”の中に、涼しさのヒントがある

特徴的な外観・間取りを持つ日本の家屋は、高温多湿な夏を過ごすうえで、実はとても理にかなったつくりをしています。
こう暑いと「エアコンいらず」はさすがに難しいかもしれませんが、古き良き知恵を活かし、自然の力をうまく借りることで、冷房に頼りきらず、朝晩だけでも自然の風で過ごすことは十分可能。
家のつくりようは夏をもって旨とすべし──。
この言葉のとおり、夏に強い家を設計することは、心地よい暮らしへの第一歩。古民家に宿る知恵を、現代の家づくりに取り入れながら、家族にとって快適な夏を丁寧にデザインしていきましょう。