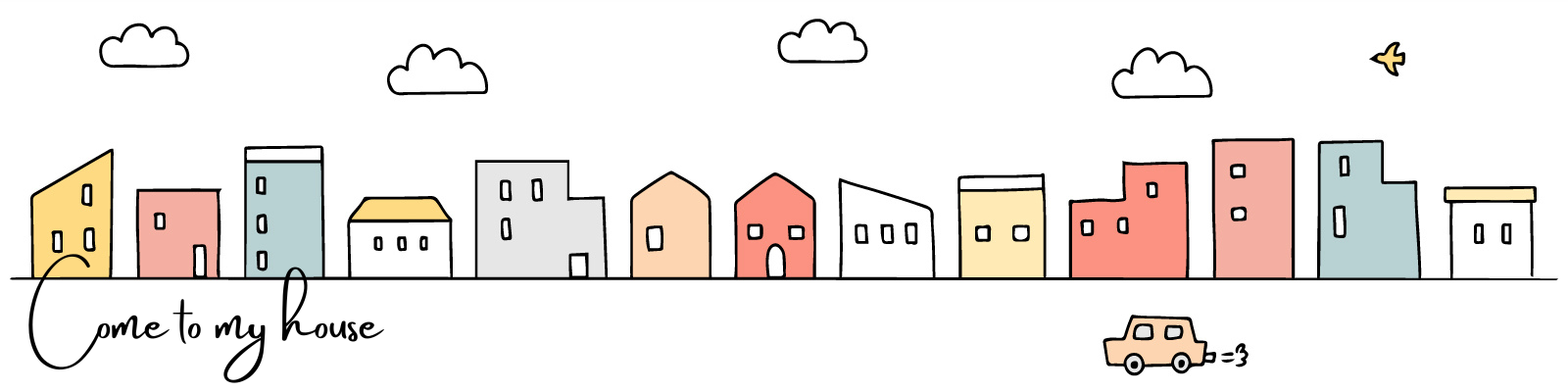もうすぐ小学校に上がる子どものいるご家庭にとって、今の暮らしにどんな“学びの環境”を整えてあげるかは、今後の学力にも直結する大切なテーマのひとつ。ランドセルや文房具をそろえるのと同じように、「どこで」「どうやって」学ぶのかを考えながら、環境づくりに取り組む必要があります。
リビングの一角に机を置くだけでもいいかもしれない。でも、その場所が“なんとなく”ではなく、子どもの性格や生活リズムに合わせて工夫された空間であれば、学びの時間はもっと心地よく、もっと前向きなものになるはずです。
無理なく、心地よく、毎日机に向かえる。そんな“スタディスペース”のつくり方を、暮らしの目線で掘り下げていきましょう。
Contents
なぜ、スタディスペースなのか?
かつては、子ども部屋に学習机を置いて、そこで宿題や勉強をするのが一般的でした。それが、どのようなきっかけでスタディスペースで学習するスタイルに移り変わっていったのでしょうか。
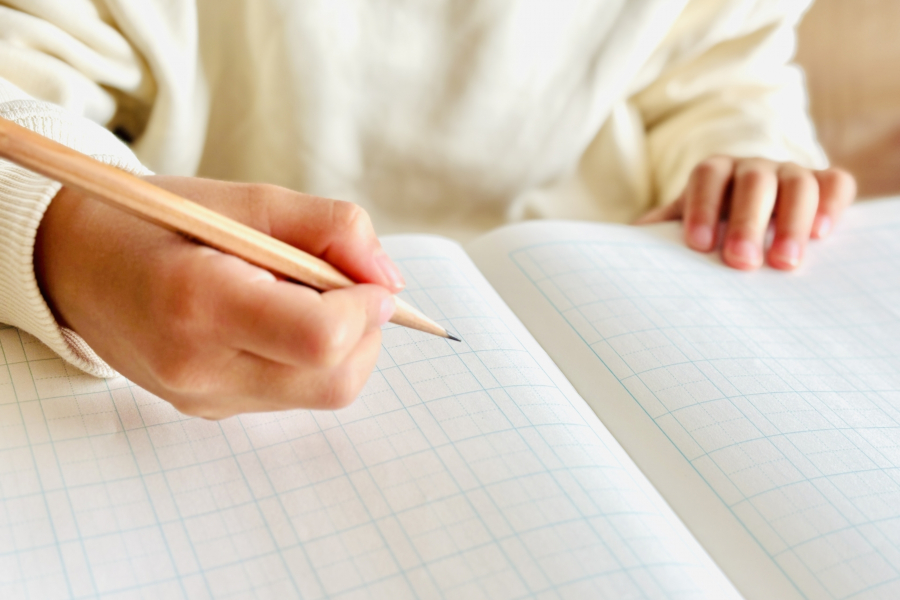
スタディスペースとは?
そもそもスタディスペースとは何なのかというと、子どもが家庭で勉強に集中できるように設けられた“学びのための場所”のこと。個室のように独立した空間ではなく、リビングやダイニングの一角に設けたオープンなスペースであることが多く、家族との距離感を保ちつつ学習習慣を育てる場として注目されています。
2000年代後半から2010年代の初頭にかけて、教育や脳科学の分野において「子どもが親の近くで学ぶ」ということの効果が提唱されるようになり、テレビ番組や書籍などで広く取り上げられたことからリビング学習が一躍ブームに。
当初はダイニングテーブルで勉強をさせるスタイルが一般的でしたが、やがてLDKの一角に専用のスペースを設ける形でリビング学習は定着していきました。
リビング学習のメリットとデメリット
今も、小学生の家庭学習にはリビング学習が効果的であるといわれています。親の目が届く場所で勉強することで、自然と学習習慣が身につき、わからないところもすぐに聞ける安心感があります。
ただし、テレビやキッチンの生活音、兄弟の声など、気が散る要素も多くなるため、集中できる工夫も求められます。一方で、生活音の中で勉強する習慣が身についてしまうと、試験中の静かな環境で逆に集中力を欠いてしまうことがあるため、中学生以上になったら個室で勉強する習慣をつけることが望ましいともいわれています。
子どもが集中できる環境とは
ポイントは“適度な距離感”。
夕方、学校から帰って宿題を広げ、わからないことがあったらすぐに質問できる環境が理想であると、当初はキッチンのすぐそばにスタディスペースをレイアウトするパターンが多かったように思います。
しかし、昨今では近すぎるのも見張られているようで集中力を欠くと、キッチンから少し離れた場所にスタディスペースを設けることが増えています。
近すぎず、遠すぎず。子どもが“自分の居場所”として落ち着ける空間づくりが、集中力を高める鍵となるようです。
学習効率が上がるスタディスペース
もう少し具体的に、スタディスペースに必要な仕様を見ていきましょう。
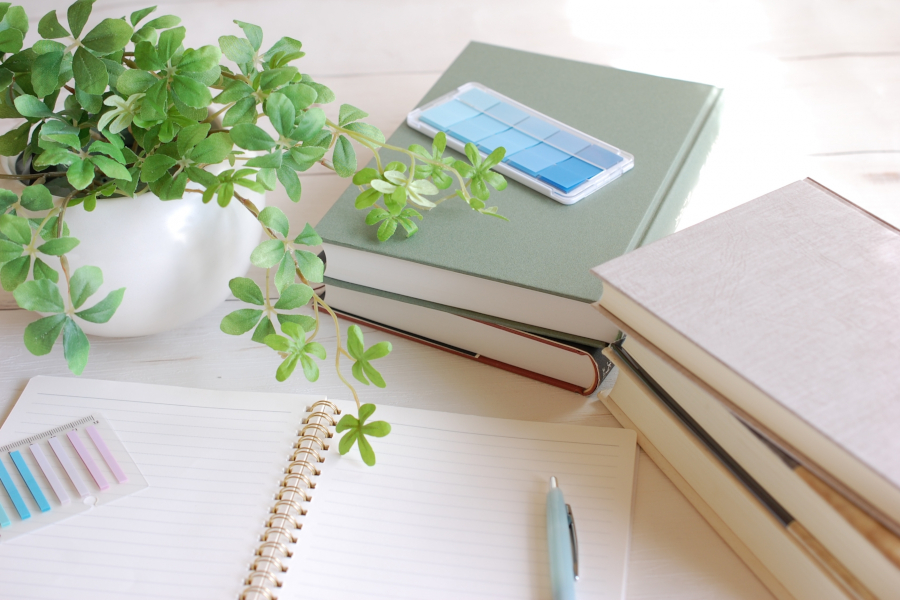
広さはどれだけ必要?
スタディスペースに広さはそこまで求められません。間仕切りのないオープンな空間であれば、間口80cm×奥行き60cmもあれば十分です。
半クローズドな空間とする場合は、全体で1~2畳程度。ただし、完全なクローズドでなかったとしても、1畳の広さの囲われた空間には圧迫感を感じる人もいます。間仕切り壁を低めにする、ガラスや格子、抜け感のある棚で緩やかにゾーニングするなど、狭さを感じさせない工夫をしてあげましょう。
デスクの奥行きと配置
机は造り付けのカウンターデスクで、テキストやノートをしっかり広げて置けるよう、奥行き45~60cmは欲しいところです。目の前に窓があると自然光が入って気持ちよく勉強できますが、時間帯によっては日差しが強すぎて集中の妨げになることも。方角や時間帯に応じて、ブラインドやレースカーテンで調整できるようにしてあげましょう。
また、背後に人の気配を感じると集中力が乱れるため、部屋の出入口が真後ろに来ないようレイアウトするか、場合によっては衝立などで目隠しを。
必要な収納と設備
収納に関しては、あとから引き出しや棚を追加することもできますから、それほどしっかりと造り込む必要はないでしょう。ちょっとした書棚やニッチをつくっておく程度で十分です。
照明は目にやさしい白色LEDを。照らす位置を変えられるスポット照明か、ダウンライトの場合は壁から20cmほど離して設置すると、頭が影になりません。
今は、ほとんどの学校でタブレット端末を取り入れた学習が行われているため、コンセントや配線孔も必須です。
注文住宅におけるスタディスペースの配置
リビング学習が流行り出した当初はキッチン近くにスタディスペースを設けるのが一般的でしたが、今はどのような場所にレイアウトするのが主流なのでしょうか。

リビングの一角に設置する
もっとも人気が高いのが、リビングの一角に設けるスタイルです。リビングと一体感を持たせつつ、格子や造作棚で “ちょっとだけ”囲ってあげると、子どもにとっても安心感のある学びの場になります。最近人気のリビングの畳コーナーも、造作カウンターを渡せばスタディスペースとして使用できます。
階段まわりを活用する
次に多いのが、階段まわりにスタディスペースを設置するパターン。リビング階段の下部はデッドスペースとなりやすい場所ですが、ちょっと“こもり感”があってスタディスペースにはぴったりです。階段の上、2階のホー吹き抜けを介してリビングにいる家族とつながる、ほどよい距離感。こんなスタディスペースなら、中学生以上になっても抵抗なく使えそうです。
そのほか、階段の途中にスキップフロアを設けて、その中間層をスタディスペースとして使用するパターンも見られます。子どもにとっては、まるで秘密基地のような特別な空間になりそうです。
通路・廊下と兼用する
スキップフロアのパターンと少し似ていますが、リビングと水まわりの間、リビングと自室の間など、部屋から部屋へ移動する廊下や通路を兼ねてスタディスペースを設けることも可能です。個室というほど閉鎖的ではないけれど、LDKからは少し距離がある。そんな落ち着いた空間は、将来的に読書コーナーや書斎として活用することも。
アレンジの余地を残しておくことが大事

スタディスペースに“正解”はありません。あれこれ思い悩んでレイアウトしても、実際に使ってみると「ここはちょっと落ち着かない」「もう少しデスクを広げたい」「窓から外が見えると集中できない」など、思わぬ課題が見えてくることもあります。
だからこそ、はじめから完璧を目指すよりも、可変性を持たせておくことが大切です。アレンジの余地を残した設計にしておくことで、あとから出てきた課題にも柔軟に対応できますし、子どもが成長してスタディスペースを使わなくなったあとも、きっと自由に活用できる空間になるはずです。