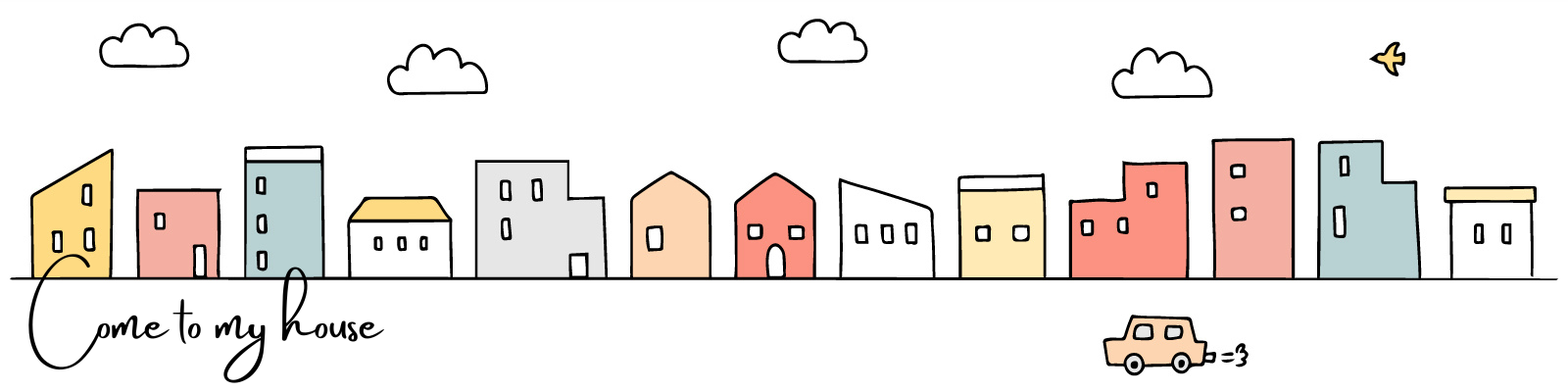マイホームの取得を検討している中、日銀が0.5%の追加利上げを発表したニュースに不安を感じている方も多いのではないでしょうか。30年、40年という長期に渡って返済が続く住宅ローンですから、「変動金利がいいと思っていたけれど、これから金利が急上昇したら…」という心配は、ごく自然なもの。
戸建て住宅という大きな買い物をするにあたって、住宅ローンの金利タイプ選びは家計に長期間影響する重要な決断になります。変動金利と固定金利、それぞれのメリット・デメリットを理解し、これからの金利環境に備えた賢い選択を!
Contents
追加利上げが住宅ローンに与える影響

2024年(令和6年)3月、日銀がマイナス金利を解除したことで、住宅ローン市場にも変化が。政策金利の引き上げは銀行の資金調達コストを上昇させるため、それが住宅ローン金利にも反映される形となっています。具体的には、変動金利に先行して動くといわれている固定金利(フラット35)が長期金利に連動して上昇傾向を見せています。
今回、日銀が0.5%という追加利上げを行ったことで、主要銀行の住宅ローンの固定金利型商品で金利の引き上げが顕著になっており、現在は据え置きになっている変動金利も今後じわじわと上昇する可能性が高いと考えられています。
これまでの超低金利時代とは異なり、金利上昇局面では住宅ローンの返済負担が増加するリスクを考慮する必要がありそうですね。
» 【2026年最新】金利上昇時代の今、住宅ローンの借り換えをすべき?
変動金利と固定金利の基本と特徴
金利選びの前に、まずは金利の種類とメリット・デメリットについて知っておきましょう。
変動金利とは

変動金利は、市場金利の変動に合わせて適用金利が定期的(通常半年ごと)に見直される仕組みを持つ、金利の種類です。一般的に固定金利より低い金利設定となっているため、当初の返済額を抑えられますが、金利上昇局面では返済額が増加するリスクがあります。
ただし、変動金利には『5年ルール』と呼ばれる仕組みがあり、返済額は5年間固定され、金利が上昇しても急激に返済額が増えることはありません(元金と利息の割合が変わります)。5年ごとの返済額見直し時に初めて金利が上昇しますが、『125%ルール』により前回の返済額から最大で1.25倍までしか増加しないという仕組みによって保護されています。
ただし、125%を超える利息については免除されるわけではないので、完済まで金利が上がり続けた場合、最終的には先送りにされた多額の利息を一括で返済しなければならないという負担が生じる場合もあります。
固定金利とは

全期間固定金利
全期間固定金利は、住宅ローン契約から完済までの全期間において、同じ金利が適用されます。代表的なのが、フラット35のような住宅金融支援機構と民間金融機関が提携したローン。
金利変動リスクがなく、金利上昇局面でも返済額が変わらないため将来の家計設計が立てやすいのが最大の特徴ですが、金利水準が高めに設定されているため、変動金利と返済額を比べた時に迷いが生じる人も多いでしょう。繰り上げ返済手数料も変動金利より高く設定されていることが多く、金利が下がっても恩恵を受けられないというデメリットもあります。
固定期間選択型(当初固定型)
一定期間(2年、3年、5年、10年など)は金利が固定され、固定期間終了後に再び金利タイプを選択するのが、固定期間選択型です。当初の固定期間中は金利上昇の影響を受けないものの、固定期間終了後は市場金利の動向によって返済額が変動します。
固定期間選択型なら少なくとも一定期間は返済額が増えないため、数年以内に子どもが大学進学するなど、大幅に出費が増えるとわかっている場合におすすめです。
今後の金利動向と選択のポイント

金融専門家の間では、日銀の金融政策正常化に伴い、変動金利も徐々に上昇であろうと予測されていますが、急激な上昇ではなく、段階的な引き上げになる可能性が高いといわれています。
興味深いのは、現時点では「数年のうちに変動金利が固定金利を追い越すことはない」という見方が強いこと。つまり、短・中期的に見れば変動金利の方が総支払額は少なくなる可能性が高いということです。
ただし、住宅ローンは30年、40年という長期間にわたるもの。この先の金融環境がどう変化するかを完全に予測することは誰にもできません。
日本の住宅ローン金利の歴史を振り返ると、約30年前の1980年代初頭には7~8%、一時的には9%を超える時期もありました。2000年代初頭でも2%前後だったことを考えると、今後30年の間に金融政策や経済状況によって金利水準が再び2%程度まで上昇することもシナリオとしては十分考えられます。
金利上昇局面での変動金利のリスク

日銀の金融政策の転換によって、これまでの超低金利時代が終わり、徐々に金利が上昇する可能性が高まっています。つまり、変動金利を選択した場合には、金利上昇によって利息部分が増え、返済総額が当初の想定より増加する可能性があるということ。金利が上がり続ければ、返済計画の見直しが必要になる場合もあるでしょう。
変動金利のリスクに備えるためには、いくつかの対策が考えられます。
①余裕をもった返済計画
収入に対する返済額の割合を低めに設定し、金利上昇時の余裕を持っておくことが重要です。
②繰り上げ返済の準備
金利上昇前に元金を減らしておくことで、将来の利息負担を軽減できます。ただし、ある程度の余裕資金は残しておきましょう。急な出費に備えて、最低でも生活費の3〜6か月分は貯蓄として確保しておくことをおすすめします。
③固定金利への借り換え
金利動向によっては借り換えも選択肢もありますが、当面は変動金利の方が得である可能性が高いため、慌てて借り換えする必要はありません。市場金利の動向を注視しながら、適切なタイミングを見極めましょう。
④返済シミュレーション
金利が上昇した場合の返済額をあらかじめシミュレーションしておくことで、心理的な準備ができます。
<返済シミュレーション>
[借入金額]3,500万円
[借入期間]35年

<変動金利の場合>
当初0.5%時の月々返済額:約88,000円
将来1.0%に上昇した場合:約93,000円(返済額見直し時)
将来2.0%に上昇した場合:約106,000円(返済額見直し時)
<全期間固定金利の場合>
2.0%で借入れた場合の月々返済額:約129,000円(35年間変わらず)
このシミュレーションから、変動金利は当初の返済負担が大幅に軽いことがわかります。また、変動金利は金利が上昇しても『5年ルール』により返済額がすぐには変わらず、5年ごとの見直し時にのみ調整されます。さらに『125%ルール』により返済額の上昇が抑えられるため、将来的に変動金利が2.0%まで上昇したとしても、その時点での返済額(約106,000円)は同じ金利水準の全期間固定金利の返済額(約129,000円)よりも低くなっています。
ただし、変動金利は将来的にさらに上昇する可能性もあること、『125%ルール』で先送りにされた利息分も最終的には返済する必要があることを含め、長期的な視点では両者のトータルコストを比較検討する必要があります。
金利タイプ選びの判断ポイント

住宅ローンの金利タイプを選ぶ際には、返済期間とライフプラン、家計の余裕度、リスク許容度などを考慮して判断することをおすすめします。返済期間が長期にわたる場合、金利変動のリスクも大きくなります。とくに、子どもの教育費がかさむ時期や老後の資金計画も考慮して、ライフプランに合わせた金利タイプを選ぶことが重要です。
月々の返済負担が家計を圧迫していないか、金利上昇時でも返済を継続できる余裕があるかを検討しましょう。月収に対する返済額の割合(返済負担率)は25%以下に抑えることが理想的です。また、金利上昇のリスクをどの程度許容できるかも重要な判断材料です。将来の金利変動に対して神経質になりやすい方は、固定金利の安定性を選ぶことで精神的な安心を得られます。
また、近年では変動金利と固定金利を組み合わせた『ミックス型』や『ハイブリッド型』の住宅ローンも選択肢として増えています。例えば、借入額の一部を固定金利、残りを変動金利にするなど、リスクを分散する方法も検討できます。この方法なら、金利上昇時のリスクを一部軽減しつつ、低金利のメリットも部分的に享受できます。ライフプランに合わせて、柔軟な返済戦略を立てることが可能です。
長期的視点と余裕を持った計画が鍵

数年のうちに変動金利が固定金利を追い越すことはないにしても、30年、40年という長期で借入する中で、金利がどう動くかわからないのは事実です。いずれにしても、変動金利もこれから上昇していくのは間違いないので、無理な住宅ローンの借り方だけはしてはいけません。子どもの学費、車の買い替えなど、将来のライフスタイルの変化まで見越して、破綻することがないよう余力を残しておくことが大切です。
住宅ローンは単なる金融商品ではなく、家族の暮らしを支える重要な要素です。変動金利か固定金利かの二択ではなく、自分たち家族のライフプランに合わせた、柔軟かつ余裕のある住宅ローン計画を立てることが、将来の安定した生活につながります。専門家のアドバイスを受けながら、金利タイプの選択だけでなく、借入額や返済期間も含めた総合的な住宅ローン戦略を練ってみてください。