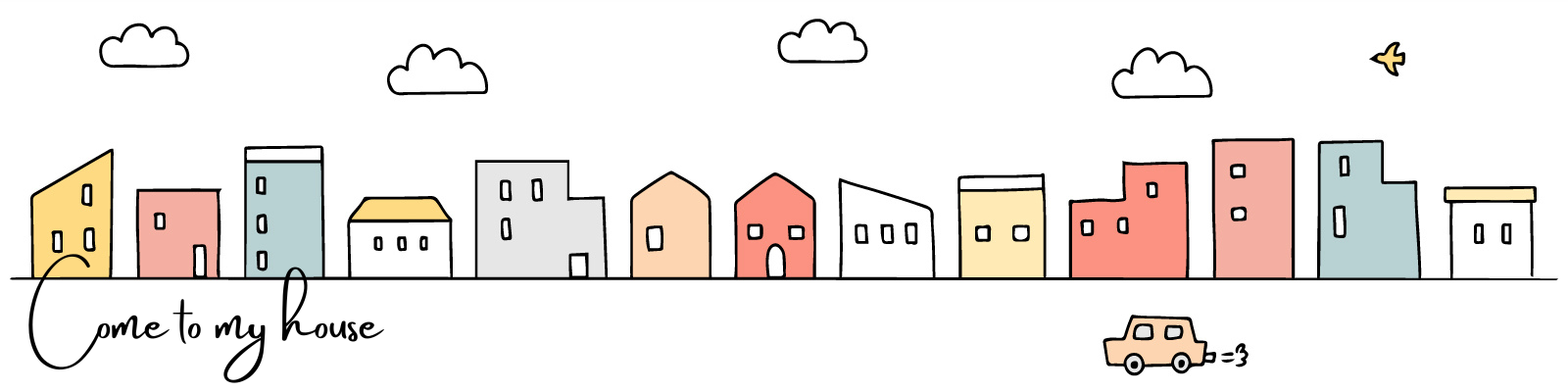マイホームを計画する際、多くの方が最初に直面するのが予算の問題です。とりわけ注文住宅は自由度が高い分、費用感がつかみにくいもの。「手っ取り早く坪単価を知りたい」というのは、これから家を新築する方の、ごく当然の心理といってもよいでしょう。
Contents
注文住宅の坪単価、実際いくら?

国土交通省の2024年度(令和6年度)建築物着工統計データによると、住宅の構造別坪単価はおおよそ次のとおりです。
| 構 造 | 坪単価 |
| 木造 | 72万円 |
| 鉄筋コンクリート(RC)造 | 115万円 |
| 鉄骨造 | 105万円 |
(出典:国土交通省|建築着工統計調査)
この坪単価から単純計算すると、35坪の木造住宅を建てた場合、
▶ 72万円×35坪=2,520万円
となり、2,500万円前後で家を建てられるということになります。
しかし、この金額で実際に家が建つケースはほとんどありません。なぜなら、この統計データにはさまざまな“落とし穴”が隠れているからです。
着工統計データの落とし穴
では、この金額にはどんな落とし穴が隠れているのでしょうか。

本体のみの金額であること
統計データの金額に含まれるのは本体工事費のみで、付帯工事費は含まれていません。
付帯工事とは、文字どおり本体工事に付帯する工事のことで、たとえば敷地の造成や整地、古家の解体費用、地盤改良工事、配線や配管を前面道路から敷地の中まで引き込む工事、外構工事などが含まれます。
付帯工事とはいえ、これらは実際に住める状態にするためには必要不可欠なものばかり。土地の現況に影響されることが多く、総額で数百万円以上、場合によっては1千万円を超えることも。
消費税別であること
統計データの金額はあくまでも本体工事の価格ですから、当然ながら消費税は含まれていません。こと注文住宅に関しては、たかが消費税、されど消費税。3,000万円の住宅であれば、消費税10%として300万円が別途必要になります。

注文住宅だけのデータではない
この統計は注文住宅に限ったものではなく、規格住宅や分譲住宅の着工統計も含まれています。
規格住宅や分譲住宅は、注文住宅と比べてコスト効率を重視したつくりになっているため、データ全体の平均金額を下げている要因となっています。
工事費予定額であること
着工統計の金額は『工事費予定額』であり、着工前に届け出たデータをもとに集計されています。しかし、当初予定されていた金額で竣工することは稀であり、多くの場合は工事中の設計変更や追加工事によって、最終的な金額が増えるケースがほとんどです。
(届出及び統計)
第十五条 建築主が建築物を建築しようとする場合又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
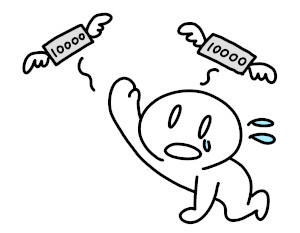
土地代・諸費用は含まれない
統計データには、当然ながら土地代や諸費用は含まれません。土地代はお住まいの地域やエリアによって大きく異なり、場合によっては建物本体と同等かそれ以上の費用がかかることも。
また、登記費用や税金、住宅ローン関連の費用、各種保険料といった諸経費も別途必要で、これらは一度にまとめて出ていくわけではないものの、トータルで総予算の10~15%程度になるといわれています。
建物予算が3,500万円なら、500万円程度は手元に用意しておきましょう。
建築基準法の改正による影響
2025年(令和7年)4月の建築基準法改正により、省エネ基準が義務化されました。また、耐震に関する規定にも変更があったため、2026年(令和8年)以降は、その分の工事費が増加すると考えられます。
注文住宅の坪単価は100万円~
住宅ポータルサイトなどで、実際の住宅の『坪単価』が公開されていますが、これらの金額も先述の着工統計データと同じ。その金額で、住める状態の家が建つわけではありません。
では、実際のところ、注文住宅はいくらで建てられるのでしょうか?

あくまでも体感的なものですが、木造住宅で坪単価100万円程度は必要だと考えられます。
5~10年ほど前までは、よほど性能やデザインにこだわった住宅でなければ、地域の工務店で建てる家が坪100万円を超えることは、あまりありませんでした。しかし、建築資材の高騰や人件費の上昇により、現在では標準的な仕様でも坪単価100万円を超えるケースが一般的になっています。
デザインや性能にこだわった家であれば、坪120万円は見ておくべきでしょう。
ただし、大手ハウスメーカーになると坪120万円が最低ラインであり、坪140万~150万円も想定の範囲内です。
注文住宅の費用を左右するポイント
あまりにも高額で、驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここからは、注文住宅の価格が上がるポイントをお伝えしていきます。

建物の大きさ
一般的に、建物が小さいほど坪単価は下がる傾向にあります。これは、キッチンやバスルームなど高コストな設備は家の大きさに関わらず必要だから。面積が広ければ、その分、単価が分散されて坪単価は下がります。最終的な判断は、坪単価ではなく総額で。
構造、性能、仕様
木造、鉄筋コンクリート(RC)造、鉄骨造など、構造の違いは大きな費用差となります。また、断熱性能や耐震性能は等級を上げるほど予算も上がりますし、住宅設備や内外装材のグレードなども予算を左右します。
デザインのこだわり
シンプルな四角い箱型の家と比べ、凹凸の多い外観や曲線を多用したデザイン、天井高の変化、大開口の窓、ディテールのこだわりなど。建築家やデザイナーが設計する住宅は、工事の複雑さから費用が高額になる傾向にあります。
立地や地盤の状態
傾斜地や軟弱地盤は、造成工事や地盤改良の費用がかさみます。また、上下水道やガス管が通っていない土地では、引き込み工事に多額の費用がかかることも。土地選びの段階でこれらを考慮することで、予想外の出費を避けられます。
“費用を抑える=安く建てる”ではない

家づくりにおいて、単に初期費用を抑えることだけが賢い選択とは限りません。長期的な視点でコストパフォーマンスを考えることが重要です。
具体的には、高断熱高気密の家や自然素材の家は建築費こそ高くなりますが、光熱費の削減や健康面でのメリット、メンテナンスの費用を抑える効果があります。
屋根材や外壁材も、安価な建材を使えば初期費用は抑えられますが、メンテナンス頻度が高かったり、耐久年数が短かったりする可能性があります。初期費用は多少かかってもメンテナンスフリーの高品質な素材や建材を選ぶことで、長期的な維持管理費用の削減につながります。
今の時代の”納得できる価格”とは

注文住宅の建築費は年々上昇傾向にあり、現在では坪単価100万円が一般的になっています。しかし、単に「高い」「安い」で判断するのではなく、自分たちが求める住まいの質や、長期的な視点での費用対効果を考慮しましょう。
たとえば、同じ35坪の家でも、3,000万円で建てるのと5,000万円で建てるのとでは、見た目だけでなく住み心地や耐久性、メンテナンス性など、さまざまな違いがあります。
大切なのは、自分たちのライフスタイルに合った最適な選択をすること。納得できる品質や暮らしの実現が、価格の妥当性を決めます。
家づくりで重要なのは、「この価格でこの家が建てられて良かった」と思える納得感。自分たちの優先順位を明確にし、そこにお金をかける一方で、こだわらない部分では費用を抑えるなど、メリハリのある予算配分を。