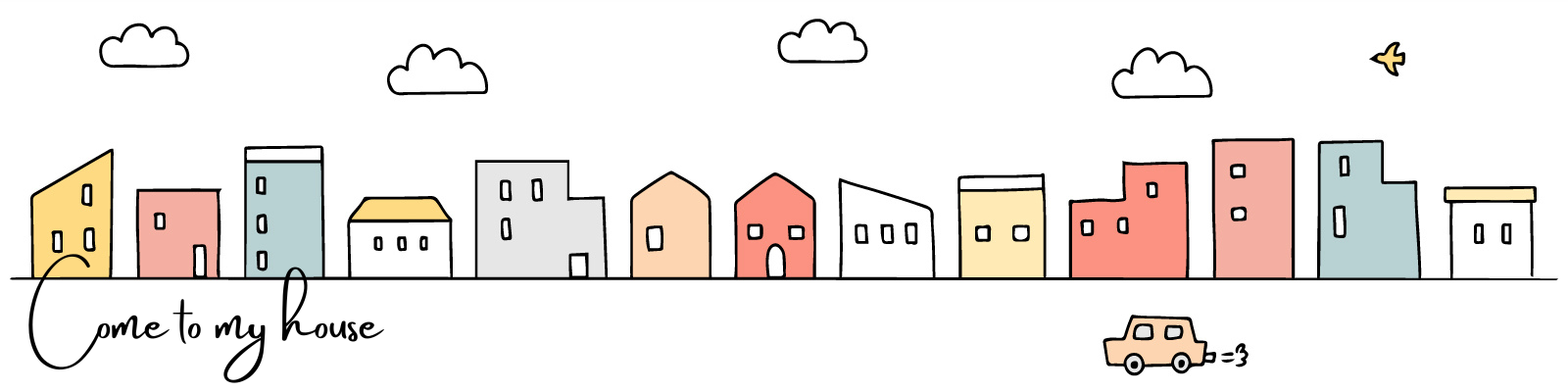最近の家は断熱・気密性能が高いので、結露しない。そんな話を聞いたことのある人も多いのでは?
確かに、一昔前のアルミサッシや単板ガラスの時代に比べれば、窓にびっしりと水滴がつくような光景は減りました。しかし、実際には新築直後の家でも結露が起こることがあります。見える場所に出てこないだけで、壁の中でひっそりと進行しているケースも――。
この“隠れ結露”は、気づかないまま家の寿命を縮めたり、カビやダニ繁殖の原因となって住む人の健康被害を引き起こしたりすることもあります。
なぜ、高性能な今の家で結露が起こるのでしょうか?
Contents
結露の基本
結露対策を考えるうえで、まずは仕組みを正しく理解することが重要です。

結露とは何か
結露は、空気中の水蒸気が冷やされて水滴になる現象です。たとえば、夏に冷たい飲み物を入れたグラスの表面に水滴がつくのも結露。空気中には目に見えない水分(湿気)が含まれていて、その空気がある温度まで冷やされると、水として現れます。この温度を『露点温度』と呼びます。
この現象は、室内でも起こります。暖かく湿った空気が冷たい窓や壁の表面に触れると、そこが露点温度を下回り、水滴が発生するのです。
冬の結露と夏の結露
家の結露は、季節によって2つのタイプに分かれます。
冬の結露
冬の室内は暖房で暖かく、湿度も高め。一方で外の空気は冷たく、室内の空気が外気に冷やされた窓や壁表面に触れて露点温度に達すると、空気中の湿気が水滴となって表れます。
夏の結露(逆転結露)
湿気を多分に含んだ夏の熱気が家の壁の内側へ入り込み、室内側の冷房で冷えた空気に触れることで、壁の内側(中)に水滴が発生します。これが、壁内結露です。
高気密高断熱住宅が「結露しない」といわれるのは、断熱性の向上によって外気の影響を受けにくくなり、かつ気密をしっかりとることで室内の空気が外へ流出しにくくなっているから。
しかし、実際には高気密高断熱住宅でも結露はゼロではありません。何が原因なのでしょうか?
高気密高断熱住宅で結露する理由
本来なら結露しにくいはずの高気密高断熱住宅。それにもかかわらず結露が起こる理由は、いくつか考えられます。

施工精度の問題
気密の甘さは結露の原因に。とくに断熱材は、隙間なく入っていてこそ効果を発揮します。施工の途中で圧縮されたり、隙間ができたりすると、その部分だけ断熱性能が落ちて冷えやすくなり、結露の発生ポイントになります。また、コンセントや配管まわりの気密処理が不十分だと、そこから冷気や湿気が侵入し、内部結露の原因になることも。
熱が逃げやすい部分(熱橋=ヒートブリッジ)にも要注意。窓の枠まわりや構造材の接合部は熱橋ができやすく、そこに湿気が集まって結露しやすくなります。
通気層の不備
建物の内側はしっかり気密をとるのに対し、外部は通気が必須。なぜなら、構造の内側に入り込んだ湿気を外へ逃がしてあげる必要があるから。
外壁通気工法による通気層の確保や床下・屋根裏の換気は、湿気を建物の外に逃がす重要な仕組み。これがないと壁内に湿気が溜まりやすくなり、内部結露の原因になってしまいます。
とくに高気密高断熱住宅の設計・施工に慣れていない住宅会社だと、通気層がきちんと施工されていない場合もあるため、注意が必要です。
換気の不足
結露を発生させないためには、家の中の湿気を効率的に外に出さなければなりません。そのために必要なのが『24時間換気』。家の性能が向上し、空気が循環しにくくなったのを機に建築基準法で義務化された換気システムですが、「電気代がもったいない」と止めてしまう人が多いという現状があります。
さらに、家具の配置で給気口や排気口を塞いでしまっていたり、基礎に設けた床下換気口の前に物を置いて、知らず知らずのうちに換気の邪魔をしてしまっているケースも。
生活習慣の影響
結露は設計や施工だけでなく、暮らし方にも左右されます。例えば、
・室内に洗濯物を干している
・加湿器を長時間使用している
・調理中に換気扇を回さないことがある
・石油ストーブなど燃焼系の暖房器具を使っている
・入浴後に浴室のドアを開けっぱなしにしている
適正な換気をせずにこうした習慣を継続することは、室内の湿度を上昇させ、結露を誘発することにつながります。
住宅新築で押さえるべき結露対策のポイント
家を建てる際には、最初から結露対策を設計に組み込むことが大切です。

窓・サッシの選び方
結露対策で真っ先に考えたいのが、窓。樹脂サッシはアルミに比べて熱伝導率が低いので、結露対策に効果的。Low-E複層ガラスやトリプルガラスを採用すれば、外気の影響を受けにくくなるため、ガラス表面の結露防止になります。
断熱と気密の施工精度
断熱材は隙間なく入れ、継ぎ目は気密シートや気密テープなどでふさぎます。配管や配線まわりの処理もきっちりと。こうした丁寧な施工が内部結露を防ぐことになるため、何より住宅会社の施工技術をしっかりと見極める必要があります。
外壁通気層の施工
内部結露をなくすには、外壁に通気層を設け、湿気を外に排出できる構造にしなければなりません。また、防湿シートと透湿シートは位置や向きを間違えると逆効果になるため、施工時のチェックも忘れずに。
温度差の少ない間取り設計
暖かい部屋と冷たい部屋があると、湿気が移動して冷えた場所で結露しやすくなるため、部屋間の温度差を減らす設計も結露防止に効果的です。全館空調を導入する、間仕切りをできるだけ少なくするなど、家の中の温度を効率よく一定に保てる工夫を。
換気システムと空気の流れ
換気は、ただ機械に頼ればよいというものではありません。家の中に空気の流れができるよう、換気経路を考えながら給気口や排気口をレイアウトするのはもちろん、家の気密性が高ければ給気口も多めにするなど、バランスも大切です。
入居後にできる結露対策

確実に結露を防ぐには、設計・施工の最適化とあわせて暮らし方の見直しも行いましょう。
洗濯物の室内干しは今や常識ですが、換気を怠ったり、燃焼系の暖房器具と組み合わたりすると湿度過多になる可能性も。
大切なのは、感覚だけに頼らずきちんと湿度をチェックすること。目安は40〜60%。冬は加湿しすぎない、夏は除湿機やエアコンのドライ機能を活用するなど、季節に応じて調整します。
調理中は換気扇を回すのを忘れずに。入浴後は浴室の戸をきちんと閉めてから、換気するようにしてください。
結露をなくす!現代の家づくりと暮らし方

結露を防ぐには、高気密高断熱設計だけでは不十分。通気や換気を踏まえた正しい設計、丁寧な施工、そして湿度を意識した暮らしが必要不可欠です。
夏と冬では結露の仕組みが違いますが、どちらにも共通して言えるのは“湿気をこもらせない”こと。
大切な我が家を長持ちさせ、健康な暮らしを守るため、見えないところで起こる結露にも気を配ってみてください。