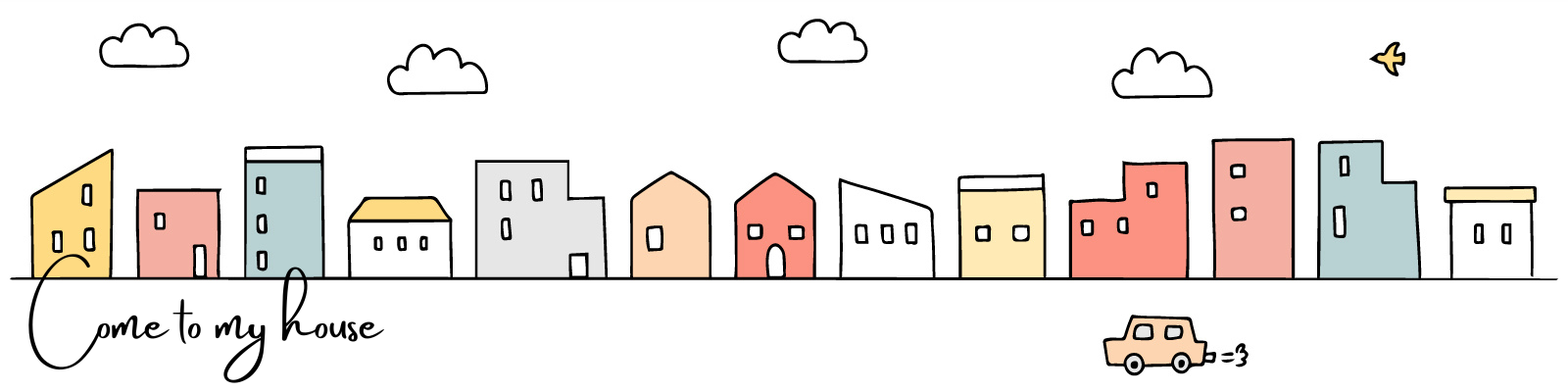私が以前住んでいた家の近所に、薪ストーブのある家がありました。毎年11月頃になると駐車場に停めてある車にうっすらと煤が積もり始め、冬の訪れを感じていたものです。
ところが、実際に薪ストーブを導入した人たちの話を聞いてみると、「後悔している」という声も少なくありません。あこがれていたはずの薪ストーブ。なぜ、後悔することになるのでしょうか。
薪ストーブで後悔している人たちの本音
あこがれの薪ストーブ。手に入れたはずなのに、なぜ後悔することになるのか。実際の声を聞いてみると、意外と”日常的なこと”につまずいている様子が見えてきます。

日々の作業が思ったより大変だった
朝、リビングで薪ストーブに火を入れる——そんな暮らしは、現実的にはそう甘くありませんでした。火をおこすには新聞紙や焚き付け用の細い薪を準備し、煙突から煙が出ないよう火加減を調整する必要があります。慣れないうちは、朝の忙しい時間に悪戦苦闘することに。
スイッチひとつで暖まるエアコンや床暖房とは違い、薪ストーブは手間がかかります。さらに使い終わったあとは灰の掃除が待っています。灰を取り出して処理する作業は週に1〜2回は必要で、これが思った以上に面倒だと感じる人も少なくありません。
「薪割りも楽しそう」と最初は思っていたけれど、実際に毎週末やるとなると体力的にもきつい。休日に家でゆっくりしたいのに、薪割りに追われる——そんな現実に直面して、後悔する人も。
薪の確保に想定外の苦労があった
薪ストーブを使うには、当然ながら薪が必要です。ホームセンターで購入すると、ひと冬分で数万円から十万円近くかかることも。「暖房費が浮くと思っていたのに、むしろ高くついている」という声も聞かれます。
自分で調達しようと思っても、薪を乾燥させるには1〜2年かかります。つまり、今年使う薪は一昨年から準備しておく必要があるのです。この計画性を持たずに始めてしまうと、湿った薪で苦労することに――。
そして意外と見落とされがちなのが、薪の保管スペース。雨に濡れないよう屋根のある場所が必要で、ある程度の広さも求められます。「庭棚が思ったより場所を取って、子どもの遊ぶスペースが狭くなった」という後悔も耳にします。薪を置く場所を確保できず、結局玄関前に積み上げることになって見た目が気になる、という声も。

「これ、ずっと続くの?」メンテナンス費用
薪ストーブ本体も決して安い買い物ではありませんが、設置後のメンテナンス費用も考えておく必要があります。煙突掃除は年に1回は専門業者に依頼するのが理想的で、費用は2〜3万円ほど。煙突内にタール(クレオソート)が溜まると煙道火災のリスクもあるため、注意が必要。さらに、薪ストーブ本体の耐火レンガやガスケット(パッキン)など、消耗部品の交換も定期的に必要になります。
導入時にこうしたランニングコストまで計算していなかった人は、予想外の出費に驚くことになります。「初期費用だけ見て決めたけれど、維持費がこんなにかかるなんて」——そんな後悔の声も少なくありません。毎年数万円のメンテナンス費用に薪代も加わると、家計への負担は決して軽くないのです。
暖かいのは、薪ストーブのある部屋だけ
「薪ストーブがあれば、家中ポカポカになるはず」——そう期待していたのに、実際は設置したリビングしか暖まらず、寝室や子ども部屋は寒いまま。これも大きな後悔ポイントです。
薪ストーブの暖房能力は確かに高いのですが、熱を家全体に循環させるには、間取りや空気の流れを設計段階で考えておく必要があります。吹き抜けやシーリングファンを組み合わせるなど、建築時の工夫がないと、熱はリビングに留まったまま。結局、寝室や子ども部屋にはエアコンやヒーターを使うことになり、「薪ストーブだけで暖房をまかなえると思っていたのに」という落胆につながります。光熱費の節約を期待していた人ほど、このギャップは大きく感じられるでしょう。
煤やにおいがもたらす、ご近所トラブル
冬になると、車にうっすら積もる煤。あれは、まさに薪ストーブの煙がもたらしたものでした。薪ストーブを焚くと、どうしても煙が出ます。風向きによっては煙が隣家に流れ、ご近隣トラブルに発展するケースも少なくありません。
住宅密集地では特に注意が必要で、近隣への配慮や説明が欠かせません。でも、どんなに配慮しても煙は出るもの。洗濯物ににおいがつく、窓を開けられない——そんなクレームを受けて、薪ストーブの使用を控えるようになった人もいるようです。
また、家の中にも薪特有のにおいが染みつきます。「キャンプ場のようないい香り」と感じる人もいれば、「洋服や髪ににおいがつくのが気になる」という人も。
後悔を避けるため導入前に考えておきたいこと
後悔している人たちの声を聞いて「やっぱりやめようかな」と思うかもしれません。でも、事前にしっかり準備しておけば、後悔のリスクは減らせます。

自分たちの暮らし方に本当に合っているか
まず考えたいのは、自分たちのライフスタイルと薪ストーブが本当に合っているかどうか。共働きで平日は朝早く夜遅い生活だと、薪ストーブを使う時間的・体力的余裕がないかもしれません。火をおこす時間も、灰の掃除をする時間も、なかなか取れないのが現実です。
逆に、週末は家でゆっくり過ごすのが好き、DIYや庭仕事も楽しめる、そんなライフスタイルなら薪ストーブとの相性は良好です。薪割りや火の管理も、趣味の一部として楽しめるでしょう。
また、家族の協力体制も大切。一人だけが薪ストーブの世話をすることになると、「夫が薪ストーブを入れたがったけれど、結局世話をするのは私」という不満も生まれます。家族みんなで役割分担できるかどうか、導入前に話し合っておきましょう。
「かっこいいから」だけでは決めない
薪ストーブは、導入を決めたら設計段階から専門家に相談していくことになります。煙突の位置や長さ、炉台や壁の耐火構造、空気の流れを考えた間取り——こうした要素を最初から計画に組み込んでおかないと、あとから失敗・後悔につながります。
たとえば、煙突が短すぎるとドラフト(上昇気流)が弱くなり、煙が逆流することも。壁との距離が適切でないと、火災のリスクが高まります。薪ストーブの専門店や、施工実績の豊富な工務店に相談しながら進めましょう。
可能であれば、実際に薪ストーブのある家を見学させてもらうのがいいですね。実物を見ることでイメージがぐっと具体的になり、写真やカタログでは分からない、リアルな使い勝手や雰囲気を体感できます。

薪をどう手に入れるか、具体的に考えておく
薪ストーブを導入する前に、薪をどう調達するか具体的に考えておきましょう。近くに薪を販売している業者はあるか、配達してくれるのか、価格はどれくらいか——こうした情報を事前にリサーチしておくと安心です。
地域によっては、伐採木を無料で譲ってくれる自治体もあります。公園や街路樹の剪定枝を薪ストーブユーザーに提供している市町村もあるので、問い合わせてみる価値はあるかも?
また、薪ストーブユーザーのコミュニティに参加するのもおすすめです。SNSや地域の掲示板で情報交換をしたり、薪の調達ルートを教えてもらったり。先輩ユーザーの経験談は、とても参考になります。
そして、忘れてはいけないのが保管場所の確保。薪を乾燥させるには風通しの良い屋根付きのスペースが必要です。図面の段階で、薪置き場をどこに作るか計画しておきましょう。
初期費用だけでなく、続けるためのお金も
薪ストーブ本体の価格だけでなく、煙突掃除や部品交換などのメンテナンス費用も含めて、年間のランニングコストを計算しておきましょう。初期費用だけ見て決めてしまうと、あとで「こんなにお金がかかるなんて」と後悔することになります。
たとえば、年間のコストを試算してみると、
薪代:5〜10万円(購入する場合)
煙突掃除:2〜3万円
消耗部品交換:1〜2万円
ざっと見積もっても、年間8〜15万円ほどかかる計算です。もちろん、自分で薪を調達したり、できる範囲のメンテナンスを自分でやったりすればコストは抑えられますが、ある程度の出費は覚悟しておきましょう。
手間も含めて、薪ストーブを楽むことが大事
一方で、薪ストーブを「導入して良かった」と感じている人は確かにいます。彼らは、薪ストーブとのように付き合っているのでしょうか。

慣れと工夫で、手間が”楽しみ”に変わった
最初は大変だった火おこしも、コツをつかむと10分ほどでできるようになります。どんな焚き付けなら火がつきやすいか、どう空気を調整すれば煙が出ないか——経験を重ねるうちに、自分なりのやり方が確立されていきます。
薪割りも、家族で協力したり、子どもと一緒に楽しむイベントにしたり。週末の朝、家族で薪を割りながら「今日はどこに出かけようか」なんて話す時間が、かけがえのないものになっていく。発想を変えることで、手間が”楽しみ”に変わっていくのです。
「最初は面倒だと思っていたけれど、今では薪ストーブの世話をする時間が好き」
火と向き合う時間が、日常の慌ただしさから離れて、自分を取り戻す時間になっているのかもしれません。
エアコンにはない、炎のある暮らしの豊かさ
薪ストーブのある暮らしには、エアコンでは得られない豊かさがあります。炎を眺める時間の贅沢。薪が爆ぜる音。家族が自然とリビングに集まってくる空気感。
そうした”目に見えない価値”を実感できるようになると、多少の手間も気にならなくなるものです。冬の夜、薪ストーブの前でゆっくり本を読む。子どもたちが炎を眺めながら、今日あった出来事を話してくれる。そんな何気ない時間が、家族の記憶に深く刻まれていく。
「薪ストーブがあると、なぜか家族がリビングに集まるんです」
そんな声も、よく聞かれます。炎には人を惹きつける不思議な力があるのかもしれませんね。
まとめ

あの日、車に積もった煤を見て感じた冬の訪れ。その光景の裏側には、薪ストーブを使う人の日々の営みがあったのだと、今ならわかります。
薪ストーブのある暮らしは、あこがれだけでは続きません。手間もコストもかかるし、近所への配慮も必要です。でも、そうした現実を理解し、事前にしっかり準備をしておけば、後悔のリスクは減らせます。
もし薪ストーブを入れるかどうか迷っているなら、実際に使っている人の話を聞いてみてください。良いことだけでなく、大変なことも含めて教えてもらう。そのうえで「それでもやってみたい」と思えるなら、きっと後悔のない選択になるはずです。
薪ストーブは単なる暖房器具ではなく、新たな趣味だと考えましょう。炎のある暮らしは、手間をかけた分だけ、豊かな時間を返してくれます。後悔している人の声に耳を傾けながら、自分たちにとって本当に必要なものかどうか、じっくり考えてみてください。